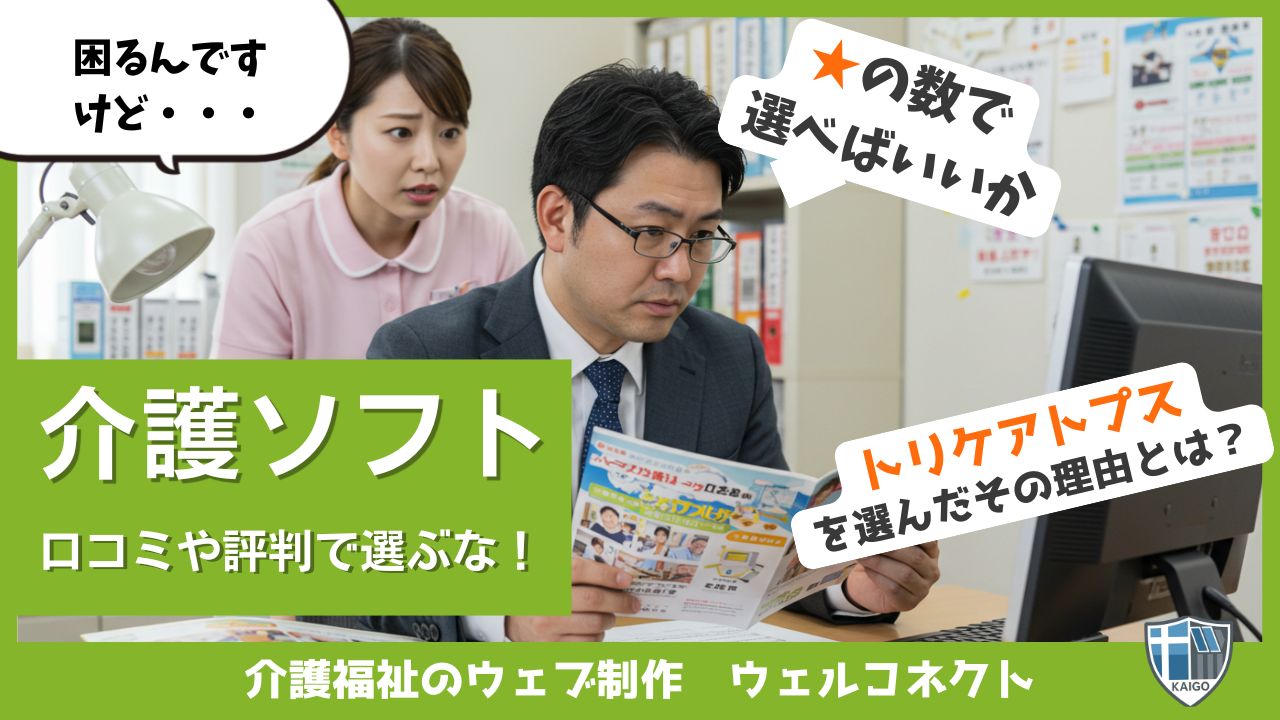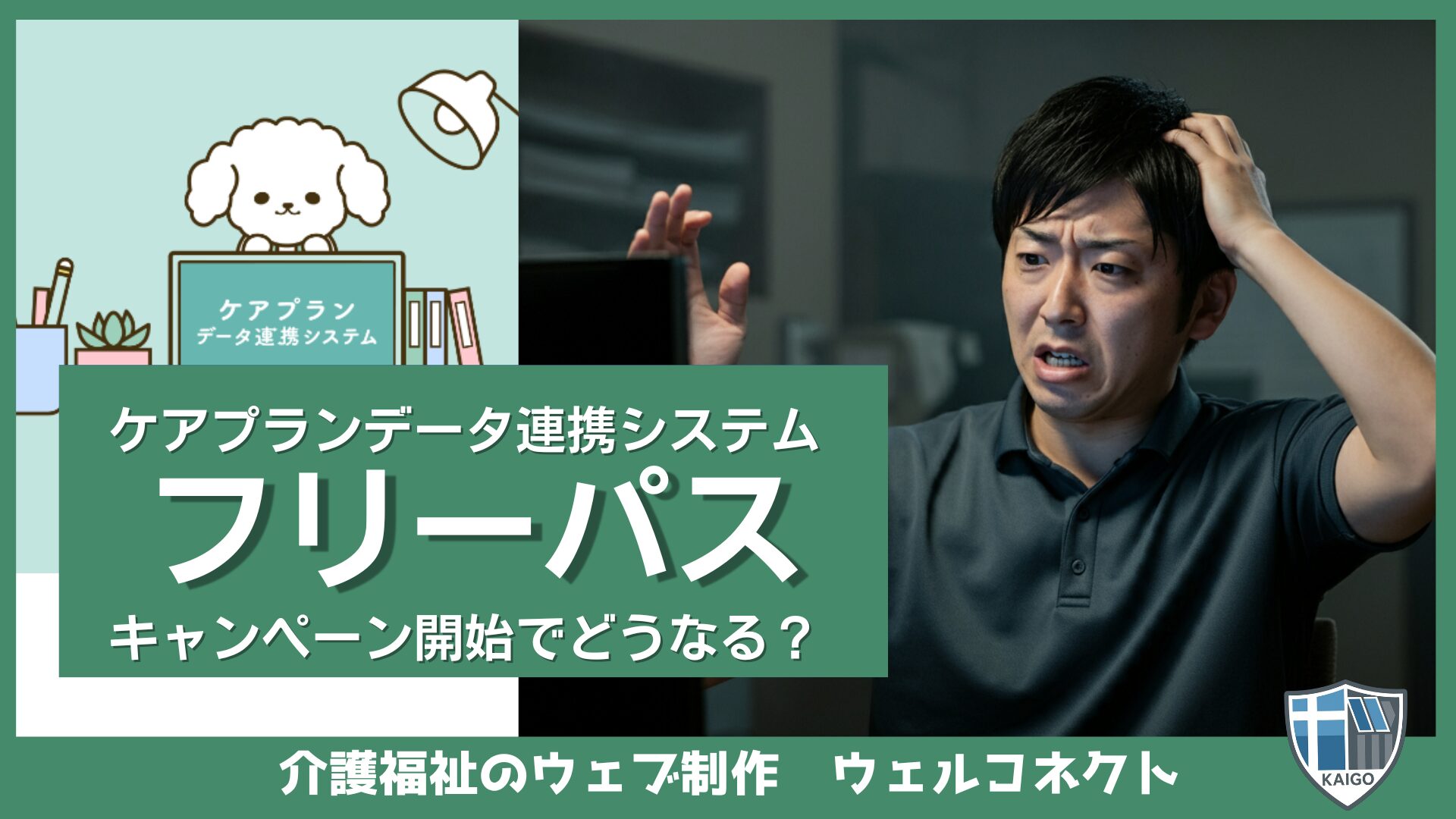介護事業所に特化したウェブ制作の事業を行っていますが、介護業界の経験が長いだけにいろいろな相談を受けることもあります。
よく相談いただくのが、介護ソフトの導入や変更について。「どれを選べばいいか分からない」という声は、小規模な事業所ほどよく耳にします。
ITスキルに長けたスタッフが限られていたり、費用に余裕がなかったりする中で、ソフト選びは事業所運営や業務効率化にも大きく影響する問題です。
私自身、かつて居宅介護支援事業所の管理者として、実際に複数のソフトを比較・導入した経験があります。
この記事では、ソフト導入で失敗しないために知っておきたいポイントを、現場目線と経営目線の両方から整理し、実体験を交えながら解説していきます。
個人的な推しソフトとして、特に小規模事業所様向けに「トリケアトプス」についての事例を紹介します。ご興味のある方は是非記事後半まで読んでいっていただければ幸いです。
この記事のコンテンツ
介護ソフト導入の期待と現実
介護ソフトを導入する事業所の多くが、「業務効率化」や「スタッフの負担軽減」を期待して製品を選びます。
特に高機能なソフトは、請求業務・記録・シフト管理・連絡機能などが一体化されており、「これひとつで全部できるなら便利そう」と感じられるかもしれません。
しかし、現実にはその“高機能”が、かえって現場の負担や混乱を招いてしまうケースも少なくありません。

複雑な操作が“日常業務に食い込めない”という壁
事業者様との会話のなかでしばしば耳にするのが、「高機能なソフトを入れてみたけど、現場ではほとんど使われていない」という話です。
その理由の多くは、“多機能=複雑”になっていることにあります。
- 操作画面が細かく分かれていて、目的の作業にたどり着くまでのクリック数が多い
- メニューが多すぎて「どこから手をつければいいか分からない」
- 慣れるまでに時間がかかり、新人やICTが苦手なスタッフが入力を敬遠する
このような状態では、ソフトが「便利なツール」ではなく、「一部の人しか使えないもの」として認識されてしまい、導入したのに活用されないという本末転倒の結果につながります。
専任担当のいない現場で“誰がITを回すのか”という現実
大規模な法人であれば、システム管理者や事務職員が導入サポートや社内研修を行うことができます。
しかし、小規模な事業所では、そうした専任人材が存在しないことがほとんどです。
多くの場合、介護職員自身がケアの合間やサービス提供後に記録を入力し、管理者が請求処理までを担うという運用になります。
そのため、複雑な操作やマニュアルを読み込む必要があるソフトは、「時間的にも精神的にも扱いきれない」という声につながってしまうのです。
とくに居宅介護支援事業所では、ひとりから数人という少人数で業務を回しているケースが多く、「業務の効率化のために入れたはずが、現場の業務時間をさらに圧迫する結果になった」という逆転現象も起こり得ます。
必要のない機能が“負担”になるパラドックス
介護ソフトには「業務連絡」「チャット」「掲示板」「シフト共有」など、便利そうに見える機能がたくさん盛り込まれていることがあります。
しかし、それらの多くはすでにLINE(LINEWORKS)などのチャットツールや、連絡ノートなどで回っている運用とかぶっており、かえって煩雑さを増す原因になります。
私がかつて管理者として使用していたあるソフトは、事業所連携やコミュニケーション機能を強化している反面、本来求めている記録や書類作成のユーザビリティが非常に悪く、効率が悪化した経験があります。
現場が本当に必要としていたのは、“毎日の記録をスムーズに入力できること”だったのです。
本来の目的からズレた付加機能に振り回されることで、
「便利そうだったけど、現場にとってはやることが増えただけだった」という結果に陥ることは少なくありません。
ソフト導入がスタッフ離れにつながることも
特に小規模な現場では、「新しいシステムに順応する余裕がない」と感じてしまうスタッフもいます。
- 「難しい操作を覚えるのが負担」
- 「入力する時間がない」
- 「前のソフトの方がよかった」
こうした声が出始めると、導入時に描いていた“効率化”や“負担軽減”という理想とは真逆の状態になります。
一部のスタッフにとっては、それが職場に対する不満やストレスに直結し、自分たちの意見を聞いてもらえない、と感じ、最終的には離職という結果につながる可能性もあるのです。
だからこそ、ソフト導入は単に機能の多さで判断すべきではありません。
現場の業務フローに自然に馴染むこと、使い続けられること、そして導入後の定着支援のしやすさを重視すべきなのです。
小規模事業所に必要なのは“ちょうどいいソフト”
機能が多ければ多いほど良い、というのは必ずしも正解ではありません。
小規模事業所では、「必要な機能だけに絞られていて、誰でも使いやすい」というシンプルさこそが、最大の価値になることがあります。
高機能=高価格というケースも多く、毎月のランニングコストが経営を圧迫することもあります。
だからこそ、「現場で無理なく使えるか」「価格に見合う運用ができるか」という視点が、ソフト選びにおいて非常に重要なのです。
介護ソフトの口コミが信用できない理由
介護ソフトを検討する際、インターネット上の口コミやランキング記事を参考にする方は多いと思います。
「○○ソフトは使いやすい!」「○○がシェアNo.1!」「業務効率化で残業ゼロを実現」といった情報に触れると、「間違いなさそう!」「求めていたのはこれだ!」と感じるのも無理はありません。
しかし、口コミや比較記事を鵜呑みにしてソフトを選ぶことは、現場にとって大きなリスクになる可能性があります。
ここでは、私が現場と接する中で実感した、「口コミに依存したソフト選びがなぜ危険か」についてお伝えしたいと思います。

介護事業所ごとに「求めるもの」がまったく違う
まず大前提として、介護事業所ごとに置かれている状況や求めている機能がまったく異なります。
つまり、ある事業所にとって“神ソフト”であっても、別の事業所にとっては“使いづらいツール”であることが十分にあり得るのです。
たとえば以下のような違いが考えられます。
- 事業所の規模感(職員5人の事業所と、複数拠点を持つ大規模法人であればもとめているものも異なる)
- サービス種別(訪問、通所、居宅、福祉用具で業務フローや記録の形式が異なる)
- スタッフのITリテラシー(若手中心か、慣れていない職員が中心か)
- 記録の優先度や現場文化(ちょっと空いた時間で入力作業を行うか、通常業務の終了後のまとまった時間に入力するか)
このように条件が大きく異なるにもかかわらず、口コミサイトや比較記事では、こうした前提条件がほとんど語られないことが多いのです。
小規模単独事業所で使用するのに、複数拠点ごとの売上進捗管理がリアルタイムで集計できる、なんて機能が必要かと言ったら必要ないわけです。居宅介護支援事業所単体であれば利用者数(介護度)と加算でほぼほぼ売上は網羅できてしまうわけですから。
事業所が違えば求める機能は異なるわけです。
比較サイトや口コミの“誰の評価か”が曖昧すぎる
もうひとつ大きな問題は、口コミの「発信者」が誰なのか明確でないことです。
- 現場職員が書いているのか
- 実際には使っていない経営者が書いているのか
- 導入して間もない初期印象だけなのか
- 法人規模やサービス種別が同じなのかどうか
こうした情報がわからないまま「使いやすい」「便利」と書かれていても、それは“誰にとっての使いやすさか”が不明瞭なままです。
また、比較サイト自体が広告掲載料によって順位が変わる仕組みになっていることも珍しくありません。
「人気第1位」や「満足度No.1」という表現に目を引かれてしまいがちですが、それが本当に中立的な評価かどうかは、慎重に見極める必要があります。
見合っていないソフト導入が「コストの落とし穴」になる
口コミや評価が良いからといって、自分たちの事業所に合っていない高額ソフトを導入してしまうケースは少なくありません。
一見すると「業務が効率化できそう」「多機能で安心」と思えるソフトでも、実際には使いこなせなかったり、機能が過剰で“宝の持ち腐れ”になってしまうことがあります。
その結果、
- 利用されないまま、毎月の高額な使用料だけが経営を圧迫する
- 必要に迫られて追加オプションを導入せざるを得なくなる
- 結局使わなくなり、数カ月後に別のソフトへ切り替え(=二重コスト・再教育コストの発生)
- せっかく補助金などを活用して導入しても、持続的な運用ができず、返って現場が混乱する
というような“コストの落とし穴”に陥ってしまうのです。
口コミやランキングを根拠に判断してしまうと、こうした実務と価格のバランスを見落としやすく、「まさかここまで使いづらいとは…」といった後悔に繋がることもあります。
“誰がどんな環境で使っていたか”が重要
私自身、居宅介護支援事業所の管理者としてソフトを選定した際、「口コミで評判のいいソフト」を複数試したことがあります。
しかし実際に導入してみると、
- 高評価されていたチャット機能がむしろ業務を煩雑にしてしまった
- サポート体制が遅く、トラブル時にまったく連絡がつかない
- 想定よりも料金が高く、経費としての持続が難しくなった
など、口コミからは見えなかった現実に直面しました。
この経験から、「良い評価が多い=どの事業所にも当てはまる」ではないということを痛感しました。
口コミは“判断材料のひとつ”にすぎない
もちろん、口コミそのものを全否定するわけではありません。
実際に使ってみた人の感想を参考にすることは大事ですし、傾向として「ここが使いやすかった」「サポートが丁寧だった」といった情報は有益です。
ただしそれはあくまで”補助的な情報”にとどめるべきであり、「口コミを鵜呑みにしてはいけない」ということも言えます。
重要なのは、「うちの事業所にとってどうか?」という観点から、
- どんな業務にどんな機能が必要なのか
- どんな職員構成でどんな使い方をするのか
- どこまでITを使いこなせるか/使いたいか
- 価格と実用性のバランスが取れているか
といった自分たちなりの基準を持った上で、最終判断を下すことです。
口コミに頼りすぎると「コスト」と「混乱」が跳ね返ってくる
介護ソフト選びは、現場運営の効率やスタッフの働きやすさ、さらには経営の健全性にも関わる重要な選択です。
その判断を「誰かの感想」や「なんとなくの評判」に委ねてしまうと、
あとから「やっぱり合わなかった」「高すぎて継続できない」といった問題に直面しかねません。口コミはあなた方の事業の成否に何の責任も持たないのですから。
だからこそ、口コミや比較記事に流されすぎず、“自分たちの現場に本当に合うかどうか”という視点で、冷静に見極めることが大切です。
小規模事業所の介護ソフト選び、3つの判断基準
小規模な介護事業所では、介護ソフトの選定がそのまま業務効率や経営の安定性に直結することが多くあります。
ところが、大規模事業所向けに設計された“高機能なソフト”を導入しても、実際には「使いこなせない」「費用ばかりかかる」といった問題が頻発しています。
そこで本セクションでは、小規模事業所にこそ必要な、介護ソフト選びの判断基準を3つに絞ってお伝えします。
あくまで“自分たちの現場”に合っているかどうか。この視点が失敗を防ぐ鍵になります。
1. 操作性:ITに慣れていないスタッフでも使えるか?

小規模事業所では、必ずしもITに強いスタッフばかりが揃っているわけではありません。
現場では、60代のヘルパーさんが記録を入力するなど、かつては紙の記録で慣れ親しんだベテラン職員が中心になることもあります。
だからこそ重要なのが、「誰でも迷わず使えるか」という操作性です。
特に見るべきポイントは以下の通りです:
- ボタン配置や画面構成がシンプルで分かりやすい
- 「入力項目が多すぎて疲れる」という声が出ない
- スマホ・タブレットでも直感的に操作できる
- 習得に時間がかからない
高機能であっても、使われなければ意味がありません。
“操作マニュアルなしでも使えるかどうか”を、特に一番ITリテラシーの低いと思われる職員の顔を思い浮かべながら確認するのがおすすめです。
2. 費用感:経営を圧迫しない価格か?
小規模事業所では、ランニングコストが経営を左右するほど重い問題になることがあります。
特に以下のようなケースには注意が必要です。
- 機能数が多いが価格も高く、使っていない機能にお金を払っている
- 請求業務だけで使っているのに、フルパッケージの料金を支払っている
- サポートが有償オプションで、追加費用がかかる
- 利用人数やデバイス数によって料金が変動する
私がかつて管理していた居宅介護支援事業所でも、併設事業所と共通するソフトを使っていた時に「機能は豊富だけど居宅介護支援事業所で使える機能ではない」「料金が高すぎる」「サポートの対応も遅く、結局業務に支障が出る」などの問題に直面していました。
重要なのは、「うちの規模や使い方にとって妥当な価格か」という冷静な判断です。
“価格が安いかどうか”ではなく、“その金額に見合った価値があるか”を見極めましょう。
3. 現場適応性:事業所の実態にフィットするか?
最後の判断基準は、「そのソフトが自分たちの業務の流れに自然に馴染むかどうか」です。
小規模事業所には、以下のような“現場ならではの特性”があります。
- 職員が少人数で複数業務を兼任している
- 業務が属人化していて、仕組み化されていない部分が多い
- 電話対応や訪問対応が多く、ソフトに向き合える時間が限られている
- そもそもパソコンが1台しかない、ということも
こうした事情を踏まえると、以下のような点が“現場に合うか”の判断材料になります:
- クラウド型で、自宅や移動中でもアクセスできるか
- ユーザビリティが高く、画面遷移が少なく、必要な情報にすぐ辿り着けるか
- 担当職員のスケジュールや記録が一元化されているか
- 現場の声に応えてアップデートがされているか
もちろん、「サポート体制」も重要です。
電話対応やチャットボット、メールフォームなど、問い合わせ方法の種類を確認しておくといいでしょう。
ソフトが原因で現場が混乱したり、不満が溜まったりしないよう、導入後のフォローも含めて選びましょう。
3つの判断軸は「うちの現場に合うか」で考える

ここで挙げた3つの判断軸――
「誰でも使える操作性」「無理のない費用感」「現場との適合性」は、
どれも“他社の口コミ”ではなく、“自分たちの実情”に照らして判断することがカギです。自分たちの理想ではなく、今の現在地、実情に照らし合わせるということです。
システムの魅力を語るのは簡単ですが、導入してから「合わなかった」と気づいても、解約や乗り換えには手間もコストもかかります。
だからこそ、小規模事業所では「最も重要な機能における操作性の高さ」があり「コストパフォーマンスが高く」「自分たちの現場の実情に合った」ソフトを選ぶことが、結果的に最良の選択になると私は感じています。
実際に使ってよかったソフトの一例:トリケアトプス
ここまで、小規模事業所にとって重要な介護ソフト選びの判断基準をお伝えしてきました。
「じゃあ、どれを選んだらいいの?」とツッコミが入りそうなので、ここからはその視点をもとに、私自身が「これは合っていた」と感じたソフトの一例として、「トリケアトプス」を紹介します。
あくまで自分の体験談として、小規模事業所での運用にマッチしていたのがこのソフトだと感じたものですし、当然、事業所の運営形態などによってはうまくいかないこともあるでしょう。
ただ、小規模の事業所様と関わる機会が多いので「ソフトって何がいいですかね?」という相談を受けると、大手ではないけれど、自分の経験として推せるのはこのソフトというのが実際のところです。
そもそも「トリケアトプス」ってどんなソフト?
「トリケアトプス」は、クラウド型の介護保険業務支援ソフトです。
訪問介護、通所介護、居宅介護支援など、複数のサービス形態に対応しており、主に中小規模の事業所を主なターゲットにしています。
他のソフトに比べて、知名度は高くありません。
自分も全く知りませんでしたが、独立型単独居宅の事業所のセミナーに参加したときに講師が使っていると話していたのがこのソフトでした。
実際に使ってみて感じたのは、「現場で本当に求めている“ちょうどいい”が詰まっている」ということでした。
操作に迷わない
まず第一に、「とにかく操作がわかりやすい」。
以前使用していた別のソフトでは、「どこから何を入力すればいいのか分からない」「帳票がバラバラで管理が大変」といった声が職員から出ていました。
一方でトリケアトプスは、画面構成のわかりやすさがあります。
そして、最初はナビゲーション機能がついているので、どこに何があるのかをソフトが教えてくれるので、スタッフに研修する際にも一から十までつきっきりで教えることもなく、スムーズに移行ができます。
コストパフォーマンスが良い
小規模事業所にとって大きな魅力は、価格設定の手ごろさです。
それ以前に使っていたソフトは月額固定料金。「使う使わないに関係なく高額なパッケージ費用を支払わなければならない」タイプでした。
トリケアトプスは、十分な機能を持ちながらも価格がかなり抑えられています。
居宅介護支援事業所では利用者数に応じた従量課金制度なので、特に事業所立ち上げの時などはソフトにかかる費用をかなり抑えることができます。だって、利用者一人当たりの料金220円/月 で、上限価格5,500円ですから。
サポート体制も手厚く、質問に対するレスポンスも早かったです(あまりサポートに相談する機会がなかったのでたまたまかもしれませんが・・・)。
「これでこの価格なら、十分に満足できる」と素直に思えたのは、他のソフトにはなかった感覚でした。
現場の声を取り入れ、複雑な業務にもスマートに対応
一番は、現場の声をよく理解していると感じることです。
多機能・高機能なソフトもありますが、大規模事業所にとっては経営面のサポートや職員管理などでメリットは大きいのかと思います。
逆にトリケアトプスはその点、現場の声を重視しているソフトだと感じます。帳票の種類も豊富で柔軟に運用することができ、業務効率を上げることができます。
また、クラウド型なので端末に縛られず、どこからでもアクセスできるのも大きなメリットです。テレワークなどでの運用にも適しています。特定事業所だったので、24時間365日利用者や事業所からの連絡がかかってくることがありますが、他のスタッフの対応についてもソフトを通して確認ができ、対応することができます。
もちろん、いま話題のケアプランデータ連携システムにも対応しています。もちろん、自分はいま現場のケアマネをしているわけではないので使ったことはないのですが。
ケアプランデータ連携システムはフリーパスキャンペーン期間中なので、ソフト切り替えのついでにケアプランデータ連携にトライしてみるのもいいかもしれませんね。
令和5年に課題分析標準項目が見直されましたが、それに対応した新しいアセスメントシートもあるそうです。こういった制度変更などに対するアップデートの小回りの良さっていうところも大きな魅力ですね。
あくまで、元ユーザーとしての体験から推しポイントを紹介しました。
トリケアトプスさんのウェブサイトはこちら
とはいえ、すでにお伝えしている通り、どのソフトにも向き不向きがありますし、事業所によって最適解は異なるでしょう。
ただ、「小規模事業所での運用で、コストを抑えながら業務を効率化したい」という条件下であれば、このソフトは非常に現実的な選択肢の一つになると感じています。
「こんなソフトもあるよ」「こういう選び方もあるよ」という一例として、参考になれば嬉しいです。
※逆に、いまいちだったソフトの情報・体験談を聞きたい人はこっそり教えますのでご相談の際にでもぜひ・・・。
選び方の“軸”があれば、ソフト選びに迷わない
介護ソフトは「高機能=正解」ではありません。
大切なのは、自分たちの事業所にとって無理なく使えて、現場の業務負担を軽減できるかどうかという視点です。
小規模な事業所ほど、操作性やコストパフォーマンス、サポートの質といった“基本の部分”がソフト選びの鍵になります。
また、口コミやランキングだけに頼らず、「うちにとって必要なことは何か?」という判断の軸を持つことが、選定ミスを防ぐ第一歩です。
ソフトの切り替えなどの際にはぜひ参考にしていただければと思います。

編集:
介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)
ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。