今回は介護事業所さんにとって気になる部分だと思いますが、「ケアマネは介護事業所のウェブサイトを見ているのか?」という問題に焦点を当ててみます。
「ケアマネって忙しいみたいだし、ホームページなんて作っても、見てないでしょ」――そんな声を、介護サービス事業者からよく聞きます。
ですが、実はその思い込みがそのチャンスを自ら閉ざしているかもしれません。なぜなら、ケアマネジャーは意外にも事業所のホームページをしっかり見ているからです。
この記事では、ケアマネがサービス事業所のホームページを見ているという事実をデータを交えて明らかにし、介護事業所が今すぐ取り組むべきホームページ改善のポイントを整理します。
この記事のコンテンツ
本当に、ケアマネはホームページなんて見ていないのか?
「介護事業所がホームページを作っても、どうせ誰も見ないんじゃないか」
——そんな疑問を持つ方は少なくありません。
実際、私たちウェルコネクトも介護業界に特化したホームページ制作を行う中で、
「高齢者がネットで検索して見るわけがない」「チラシや口コミで十分」といった声をよく耳にします。
たしかに、介護保険サービスの利用者は主に高齢者です。
(第二号被保険者を含めても40歳以上が中心。)
“利用者本人”が自らスマホやパソコンで検索して問い合わせをするケースは、まだ多くないのも事実でしょう。
ただし、ここで見落とされがちなのが——
ホームページの本当のターゲットは、利用者本人ではないという点です。
ホームページを見ているのは「介護を支える側」の人たち
介護事業所のウェブサイトを訪れるのは、
- ご家族など、介護の判断を担う人
- 求人情報を探す介護職員や学生
- そして ケアマネジャー(介護支援専門員)
この3つの層が中心です。
その中でもケアマネは、事業所との関係づくりや紹介の判断に直接関わる、いわば「紹介の入口」。
だからこそ、ケアマネがどのようにホームページを見ているかを知ることは、
集客や信頼づくりにおいて欠かせない視点になります。
「ケアマネは見ていない」という思い込み
介護業界ではいまも、「ケアマネは現場で忙しいし、結局は顔見知りの事業所に紹介する」と考えられがちです。
しかし、介護専門誌『介護ビジョン』(2021年7月号)の特集で「ケアマネジャーに聞きました 介護事業所のWebサイト、どう見ている?」というアンケート集計の結果が掲載されていることです。
「介護事業所のWebサイトを業務で見ますか?」という質問項目では、
「見る」が83%、「見ない」が17%という結果でした。

地域介護経営 介護ビジョン 2021/7月号―介護を変える多面的介護経営情報誌
8割以上のケアマネが業務として介護事業所のウェブサイトを見ている!という結果でした。
また、端末はパソコン(デスクトップ・ノート)が75%と圧倒的に多いという結果でした。
つまりケアマネは、人間関係のつながりだけで事業所を選択しているのではなく、
ホームページを閲覧して情報収集し、担当者から聞き取れていなかった情報を確認しているのです。
ケアマネが検索するのは、“紹介のための確認作業”
ケアマネが事業所を検索するタイミングは、主に次のような場面です。
- 新規利用者に合うサービスを探すとき
- 加算・専門職配置・提供エリアを調べたいとき
- 連絡窓口や担当者名を確認したいとき
- 苦情や相談があったとき、事業所の方針を確かめたいとき
どれも「安心して紹介できるか」を判断するための行動です。
つまりホームページは、営業のためではなく、信頼を確かめるための窓口として見られています。
ケアマネは介護事業所のウェブサイトを見ている。
ケアマネなんて、おばあさんに片足突っ込んでいるような人がほとんどだから(失言)、インターネットなんてしないんだろうと考えている介護事業者の皆さんはまず考え方を改めた方がいいかもしれません。
新型コロナウイルスの影響もあり、事業者が居宅介護支援事業所に営業することがあまりできなくなったのと同様、ケアマネも感染対策を考慮して、事業所を訪問する機会が少なくなっていると思います。
在宅テレワークなどをするケアマネも多いと思います。事務所にあるデイサービスのパンフレットが手元にない、あ、ホームページ見ればいいか!ポチとインターネット上で検索をするという行動をとるケアマネも増えているでしょう。

ケアマネがホームページでチェックしているポイント
ケアマネが事業所のホームページを開くとき、
最も重視しているのは「いま担当している利用者に合うかどうか」。
サービスの善し悪しを比較しているわけではなく、
「この方を安心して通わせられるか」「自立支援の方針と合っているか」を確かめています。
利用者とのマッチングを確かめるための情報
たとえば——
- 認知症がある方の場合:どの程度まで対応できるのか。認知症専門スタッフがいるのか。
- 通所サービス(デイ)なら:利用時間やプログラムが合いそうか。
- 加算などを踏まえて、負担限度額の中でサービスが組めるかどうか。
- 訪問介護や訪問看護で男性スタッフがいるかどうか。
- 訪問看護やリハビリなら:PT・OT・STなどの専門職が在籍しているか。
こうした情報が、ホームページにきちんと書かれていれば、
ケアマネはわざわざ電話で確認する必要がありません。
むしろその方が早く・正確に判断できる。
だからホームページは、
ケアマネにとって“紹介先の候補を探すため”というより、
利用者一人ひとりに合った事業所を見極めるための業務ツールなんです。
電話で聞くよりも、ホームページの方が確実な理由
電話で質問しても、担当者が不在だったり、
聞き方によって回答が変わったりすることがあります。
一方、ホームページに情報が整理されていれば、
ケアマネは業務の合間に確認し、他の候補と比較しやすい。
「問い合わせる前に一度ホームページを見る」
——これは、忙しいケアマネにとって当たり前の行動になっています。
ホームページが整っている事業所は、
それだけで「連携が取りやすそう」「情報が信頼できそう」という印象につながります。
情報の整理が「信頼の土台」になる
つまり、ケアマネは“見ていない”のではなく、
自分の利用者を守るために見ている。
そこに必要なのは、派手なデザインでも宣伝文句でもなく、
「この人に合うか」を判断できるだけの具体的な情報です。
ケアマネはホームページの情報を重視する
もう一度言います。ケアマネは介護事業所のウェブサイトを見てます。
(※かくいう自分も主任ケアマネ持ってますから)
アンケート自体がウェブアンケートだったので、回答者の偏りはあったかもしれませんが、いずれにしてもケアマネにとってウェブサイトは貴重な情報源になっているということがわかります。
なので、ケアマネに向けて、ケアマネが求めているであろう情報をまとめたケアマネ用ページを作るというのもひとつの戦略です。加算内容や緊急時の対応、情報連携の手段などを細かく掲載しておくと、安心して繋がることができるでしょう。
まだまだウェブサイトを持っていない事業者も多いこの業界。
ウェブサイトは「あればいい」という時代から早く脱却して、明確なメッセージを伝える訴求力を持ち、他の事業所との差別化ができるホームページが主流になることを期待します。

編集:
介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)
ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。
お問い合わせフォーム
サイト制作やリニューアルに関して、ご相談だけでも構いませんので、どうぞお気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。



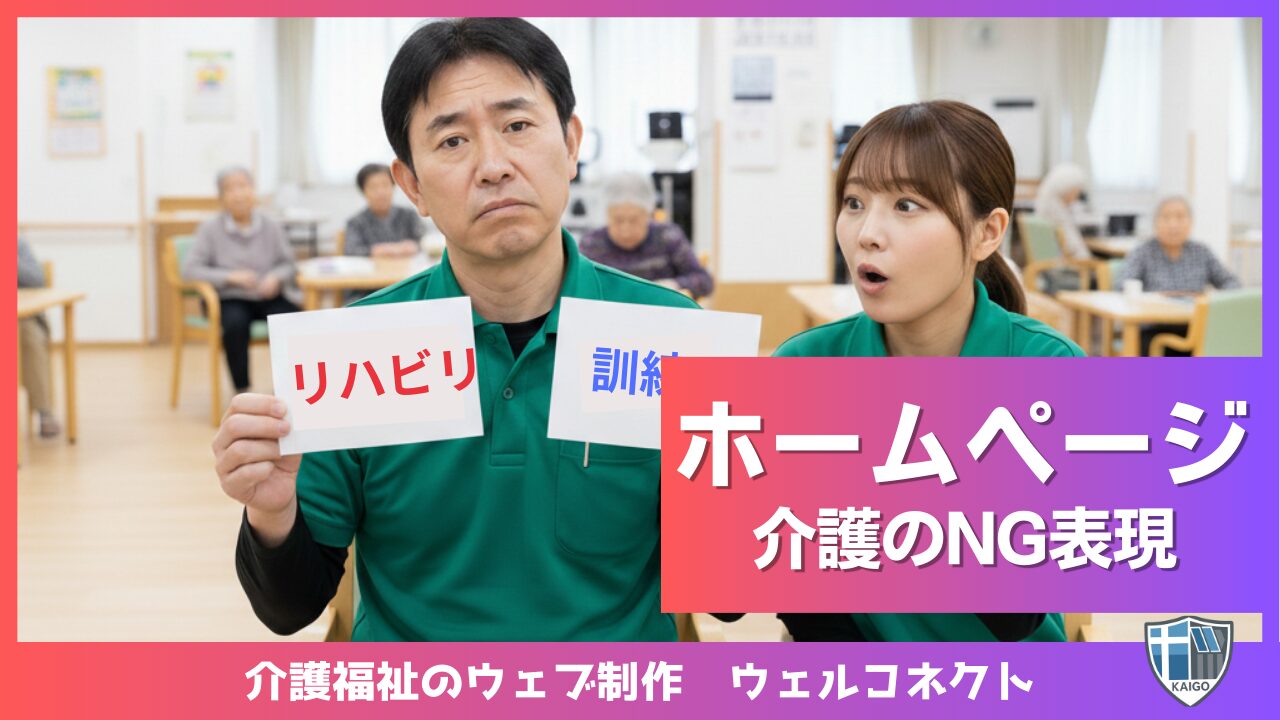

“実は“見られている” — ケアマネが介護事業所のホームページをチェックしている根拠と理由” への1件のフィードバック