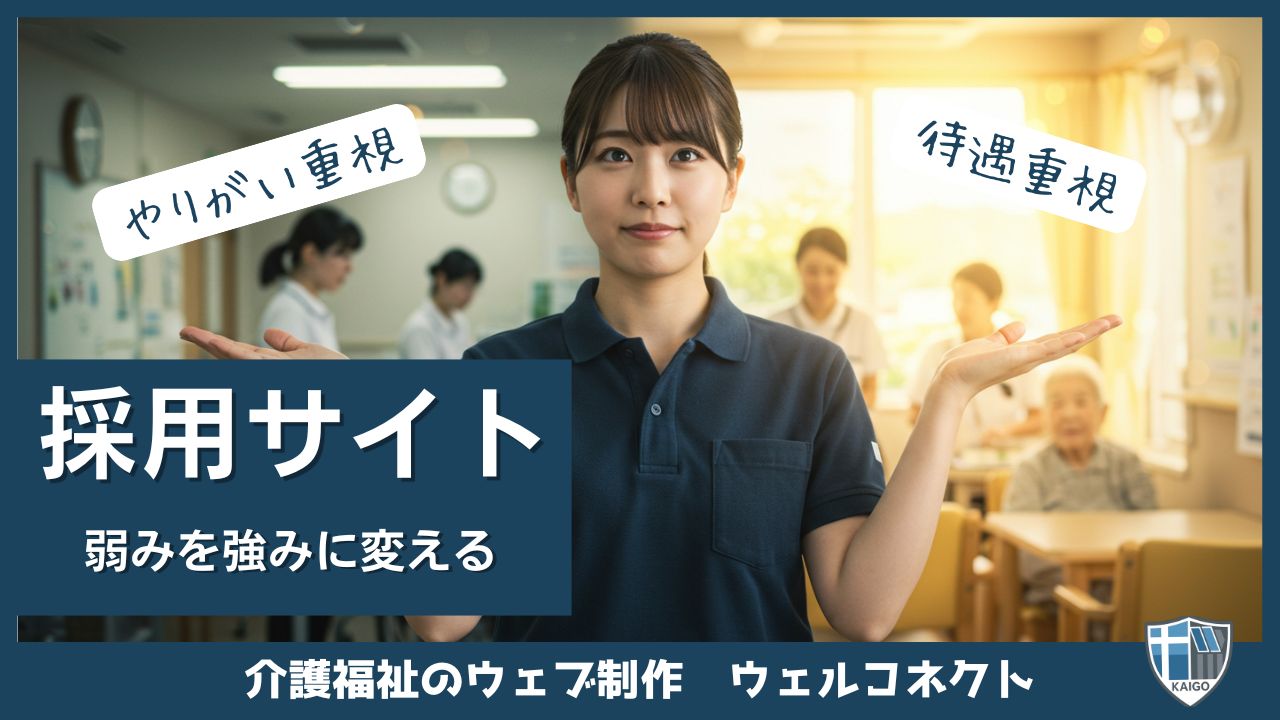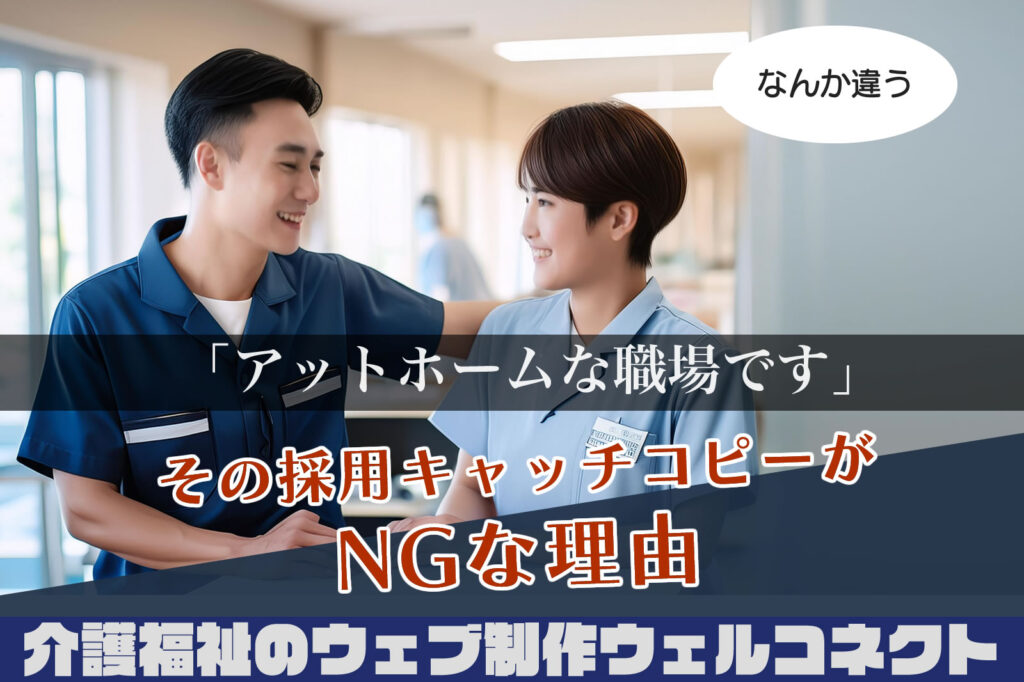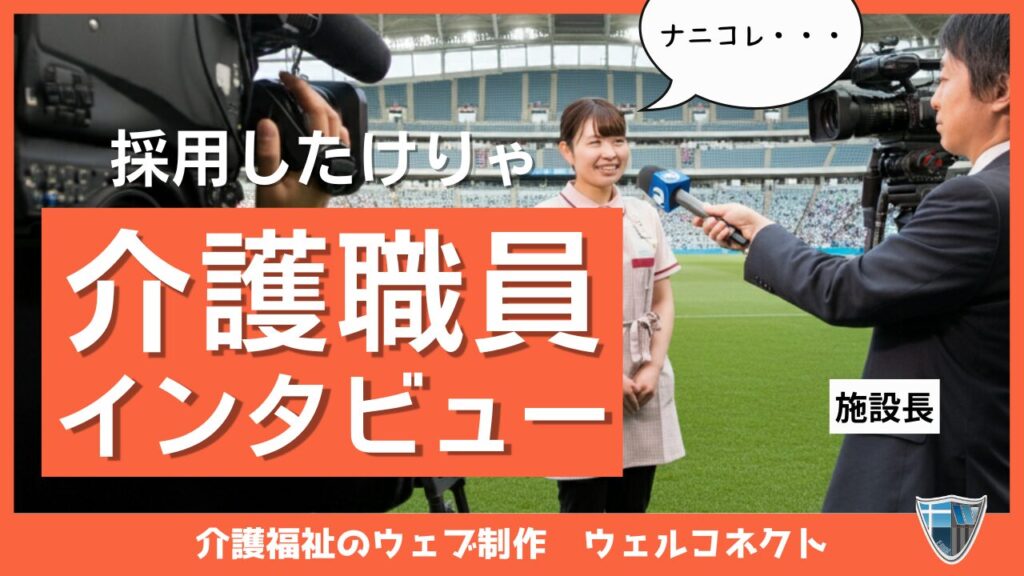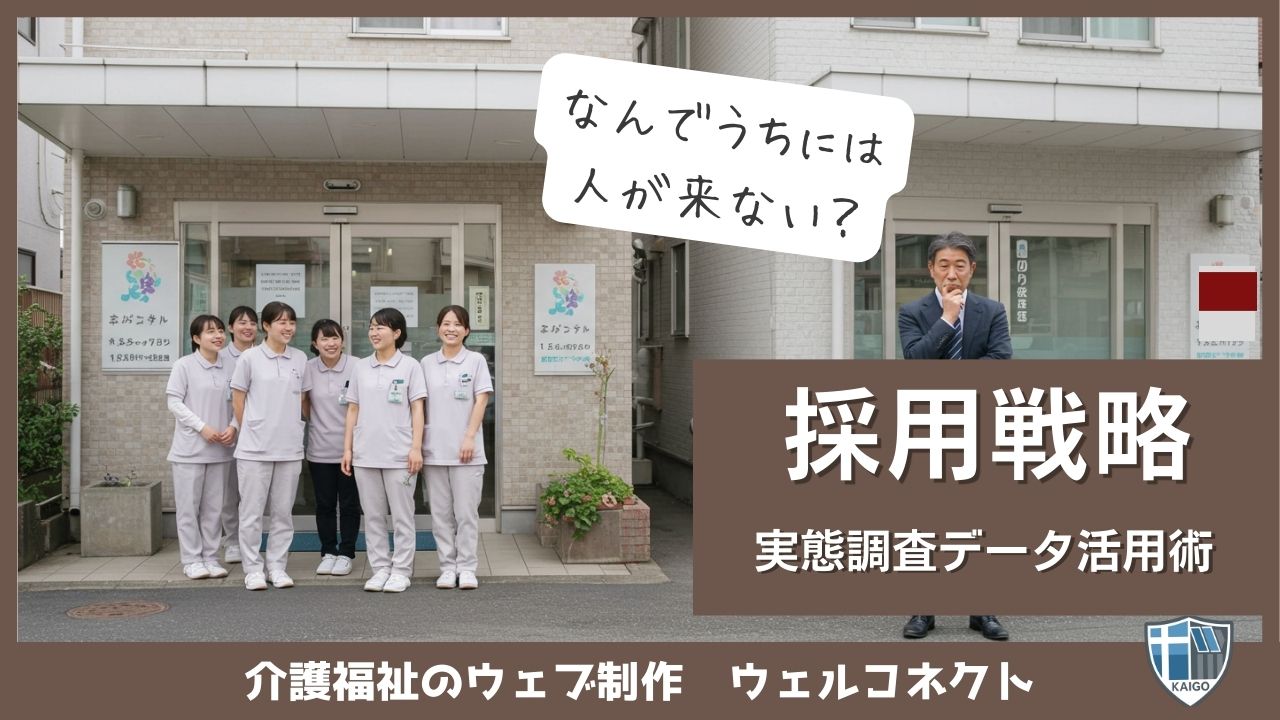介護人材の確保は、もはや「難しい」では片づけられない深刻な課題です。
- 2023年7月時点、「介護サービス職」の有効求人倍率は 3.88倍。全職業平均の 1.15倍 を大きく上回り、全国の介護現場が慢性的な人材不足に直面していることがわかります。
- 厚生労働省の推計では、2025年度には 約40万人、2040年には 約57万人 の介護職員が不足するとされています。
- 都市部ではさらに競争が激化し、採用そのものが「至難の業」という声も珍しくありません。

そんな中で、私が介護事業所の採用サイト制作に携わっていて感じるのは、「いいことだけが書かれたサイト」の多さです。
確かに、明るい写真や前向きなメッセージは必要です。しかし、現場経験のある求職者は、そんな完璧な職場は存在しないことを知っています。
さらに、介護サービス情報公表システムを覗けば、離職率・職員数・処遇改善の取り組みといった数字は誰でも確認できます。
「サイトには魅力的なことばかり書いてあるけれど、実際は離職率が高い」という事実は、応募前にあっさり見抜かれてしまうのです。
仮に採用段階でバレなかったとしても、入職後に現実とのギャップが露呈し、信頼関係が築けないまま早期離職へ――。
これは採用コストや教育コストの損失だけでなく、残された職員の士気低下にも直結します。
だからこそ、採用サイトは「宣伝」ではなく、「現状とこれから」を正直に伝える場であるべきです。
完璧を装うよりも、課題と改善への取り組みを示し、弱みを強みに変えて見せるほうが、結果的に応募者の質と定着率を高めます。
この記事のコンテンツ
なぜ弱みを出すのが採用に効くのか
1. 経験者ほど“現場の大変さ”を知っている

介護職経験者は、入浴介助や夜勤、急な体調変化への対応など、日々の業務にどれほどの体力・精神力が求められるかを肌で知っています。
忙しい時間帯の慌ただしさ、シフト変更の急なお願い、利用者や家族との難しいやり取り――これらは現場に立ったことがある人なら誰もが経験したことです。
そんな人たちに「大変なことは何もない」「毎日笑顔でハッピー」「ここで働けば楽して成長できる」といった理想像だけを見せても、現実とのギャップを瞬時に察知します。
「そんな職場は存在しない」「入ったら本当は大変なんだろう」と不信感を抱かせ、応募をためらわせてしまうのです。
経験者が求めているのは“理想の絵”ではなく、“現場のリアル”と“それをどう乗り越えようとしているか”なのです。
2. ネガティブ情報を出す=誠実さの証明
採用サイトには、いいところ・キラキラした部分だけを表現するのではなく、事業所の弱みと思われる部分も掲載することをお勧めします。きっと、多くの経営者や管理者から見たら、自ら弱点をさらす行為のようで抵抗を感じるのではないでしょうか。
しかし、それは同時に「私たちは隠し事をしない職場です」という誠実さ・強さの証明でもあります。それでも揺るがない信念や誇りを持って、この事業を成長させていきたい。そんな思いを表現していくことが大事です。
介護の現場で働く人は、困難があること自体には驚きません。キラキラした理想郷のような職場がないことは誰でも知っているのです。
3. ギャップが少ない=定着率の向上
介護業界の離職理由の上位には、必ずといっていいほど「入職前に聞いていた話と違った」が挙がります。
仕事内容や人間関係、シフト体制――こうした情報を事前に正直に共有していれば、求職者は納得した上で応募します。
結果として、入職後の満足度が高まり、離職率が下がります。
これは採用活動の回転数を抑え、教育コストや人材紹介料などの経費削減にも直結します。
“正直さ”は、採用コストを下げる経営戦略でもあるのです。
4. 介護業界特有の「見える化」
介護サービス情報公表制度や処遇改善加算の公表義務によって、事業所の離職率や職員数、研修の実施状況などは誰でも閲覧可能です。
さらに、口コミサイトやSNSでも職場の評判が共有される時代。
「定着率に自信」「長く働き続けることができる職場」と採用サイトでいくら書いても、事実を曲げることはできません。
今の時代、「弱みを隠す」という選択肢は、もはや現実的ではありません。
ならば、自分たちから弱みと思われる部分も開示し、「今こういう課題があり、こう変えようとしている」という改善のストーリーを伝えるほうが、情報の主導権を握れます。
情報は隠す時代から、活かす時代へ。
採用サイトは、その変化を最も効果的に体現できる場なのです。
弱さを強みに変える「リフレーミング」
直球すぎる弱みばかりを書くことには注意を

弱みをそのまま書くと、読む側は「大丈夫かな?」と不安になることもあります。あまり弱みが多く書かれ過ぎていると、それって、致命的なんじゃないか、と感じてしまうでしょう。
ここで役立つのがリフレーミングの手法です。
これは物事の捉え方や言い回しを変えて、前向きな意味を付け加える技術。介護現場では、ケアマネジャーや生活相談員など、相談援助職が日常的に利用者・家族との面談で使っている馴染み深いコミュニケーションスキルです。
ネガティブなワードは別の視点から見ればポジティブな要素に見えます。弱点があるというのは言い換えれば「まだまだ伸びしろが十分にある」ことを意味しているのです。
人材採用に使えるリフレーミングの例
採用に効くリフレーミング例を一部紹介します。
| 現状の弱み・課題 | リフレーミング例 |
|---|---|
| 離職率が高い | 個人に業務が属人化しないシステム化が進んでおり、誰でもスムーズに業務を引き継げる |
| 駅から遠い | 静かな環境で落ち着いて働ける/車通勤しやすく、通勤ラッシュに巻き込まれない |
| 利用者数が多い | 多様なケースに触れ、短期間で経験値を高められる |
| ICT化が遅れている | 新しいシステム導入の初期メンバーとして関われる |
| 若手社員が少なく、職員が高齢化している | 豊富なノウハウを直接学べる環境 |
| 中核的な存在となるベテラン職員がいない | 新しい発想や柔軟な働き方を取り入れやすい雰囲気 |
| 夜勤体制が不十分 | 夜勤専従スタッフ採用中で、負担軽減を計画的に実施中 |
| 休憩スペースが狭い | 外出や近隣施設で気分転換しやすい立地 |
| 研修制度が未整備 | 外部研修や勉強会など、自分に合った学び方を選べる |
| 職員同士の意見の衝突が多い | 活発に意見を交わす風土があり、業務改善のきっかけが多い |
| 管理者が現場にあまり入らない | 各スタッフが自律的に動ける裁量がある |
| 利用者家族からの要望が多い | 家族とのコミュニケーションスキルを磨ける場が多い/ユーザーニーズが顕在化しやすい |
| 繁忙期の残業が発生する | チームで助け合いながら業務を乗り切る団結力がある |
| 建物や設備が古い | 現場の声を反映した改修計画を立てやすい状況 |
このようなリフレーミングを使うと、弱みは決して致命的な問題ではないと感じやすくなり、また、より職場の解像度が高くなります。
リフレーミングは“弱みを隠す”のではなく、“現状と改善への取り組み”を前向きに伝えるための補助輪の役割を果たします。
現状、夜勤スタッフの数は十分とはいえませんが、負担軽減を目的に専従スタッフの採用を進めています。新しい夜勤体制が整えば、日中スタッフも含めた業務のバランス改善につながります。
このように、課題→改善意識→期待できる効果、の順で伝えることで、マイナス情報が「成長のストーリー」に変わります。
言い換えだけでは終わらせない、「改善の姿勢」を示す
ここまで見てきたように、弱みはリフレーミングによって魅力に変えられます。
実際、表現を変えるだけで「本当に弱みなのか?」と思えてくるケースも少なくありません。
しかし、どれだけ巧みに言い換えても、改善すべき課題は残ります。
「夜勤体制の不足」「高い離職率」「研修制度の未整備」などは、放置すれば現場の負担や利用者への影響が大きくなるため、長期的には必ず改善が必要です。
だからこそ採用サイトでは、
- 現状を正直に共有する
- 課題に対して具体的な改善計画を示す
- 応募者がその改善の一員になれる可能性を伝える
この3つを組み合わせることが重要です。
「改善ストーリー」への共感を生む

現代の採用では、待遇や条件だけでなく、課題解決の物語に共感して応募する人が増えています。youtubeやtiktokなどの動画を採用のためのプロモーションに活用し、そのストーリーに共感する人を採用するパターンが増えてきています。
特に介護業界では、理念や価値観だけでなく、「課題→改善計画→進捗→成果」という流れにリアリティがあるほど、求職者は自分事として感じやすくなります。
- 文章で示す
例:「夜勤体制は現在2名ですが、2026年度までに3名体制への移行を計画しています。」 - 数字で示す
例:離職率の推移や改善目標をグラフ化して公開。 - 現場の声を添える
例:「シフトの柔軟性が上がり、家庭との両立がしやすくなった」といったスタッフの声。 - 時系列で見せる
例:ICT化の導入プロジェクトをタイムライン型で紹介し、改善の進捗を共有。
こうした改善ストーリーは、「この職場なら変わっていく過程を一緒に経験できそう」という前向きな印象を与えます。
働くすべての人が、完全に出来上がった環境に身を置きたいと思っているわけではありません。新たなチャレンジをしたい人、達成するのが難しい目標を達成したい人、世間からも厳しく批判されている場所に自ら身を置いて立て直したい人、など、本当に様々です。
特に女性の多い介護職・看護リハビリ職などは、待遇よりもやりがいを重視する傾向が多く、そのプロフェッショナルとしての意識の高さに火をつけることができれば、採用と同時に事業所にとっての大きな力を得ることになります。
つまり、弱みを魅力に変えるだけでなく、その先にある“変化の物語”まで見せることが、信頼と共感を生む採用サイトのカギです。盛り込むことで、「この職場は変わろうとしている」という確信を求職者に与えられます。
まとめ
介護業界の採用は、かつてないほど厳しい環境にあります。
そんな中で「いいことだけを並べたキラキラした採用サイト」は、求職者からすれば現実味がなく、場合によっては不信感すら与えます。
だからこそ、採用サイトには次の3つが必要です。
- 現状を正直に共有する勇気
- 弱みを魅力に変えるリフレーミングの発想
- 改善に向けた具体的なストーリーを示す姿勢
弱みを隠さず、改善の道筋を物語として見せることで、求職者はその過程に共感し、「この職場なら一緒に働きたい」と感じます。
これは単なる求人情報を超えて、事業所の理念や価値観、未来像を共有する採用戦略です。
ウェブ制作の立場から見ても、この“弱さを強さに変える設計”は、サイトをただの宣伝媒体ではなく、人と人をつなぐ信頼の場に変えます。
課題を正直に語り、改善の物語を共に描くこと――それこそが、介護事業所の採用サイトの目指すべき理想ではないでしょうか。

編集:
介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)
ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。