この記事のコンテンツ
介護現場にいたら必ず経験する事故報告書
事故報告書、できれば書きたくないですよね。でも、介護の仕事をしていたら絶対に避けては通れない事故報告書。
介護の現場では様々な事故リスクがあります。
転倒、誤嚥・窒息、誤薬・与薬もれ、異食、医療処置、情報漏洩など、様々なリスクと日々隣り合わせの業務をしているのです。転倒なんて、介護が必要な高齢者を相手にしているのだから、日常的に起こりうることなんですけど、事故は事故になってしまうんです。

そして、事故報告書を書くのは当事者だけでなく、第一発見者が書く場合もあります。
「私じゃないのに・・・。」
そんな思いをしながら勤務時間外に泣く泣く事故報告書を書いた経験ありませんか。
事故の原因を作った介護職員は、厳しく追及される・指摘を受けることこともあります。介護職員一人のせいではなく、多くはシステム上の欠陥などが影響しているのですが、やはり自分が責められていると感じてしまう介護職員も多いです。
このような事故をめぐるつらい経験からバーンアウトしてしまう介護職員もいます。
つらい仕事はAIに ― 事故報告書に感じる負担を軽くする
介護の現場で働いていると、どれだけ注意していても事故やヒヤリ・ハットは起きてしまいます。
そのたびに求められるのが「事故報告書」。
利用者やご家族、上司、行政への説明など、誰に見られても誤解のないように書く必要があります。
でも実際には、書くたびに時間がかかり、精神的にも負担が大きいという声が多い。
「文にするのが苦手」「責められている気がする」「まとめる時間がない」──
そんな“報告書疲れ”を軽くしてくれるのが、AIのサポートです。
AIが介護現場の「つらい仕事」に向いている理由
AIは単に効率化のためのツールではなく、負担のかかる業務を整理し、人が本来の仕事に集中できるようにする仕組みです。
介護業務の中でも、「事故報告書」は特にAIの得意分野といえます。
1. 感情に左右されず、客観的にまとめられる
報告書では「言葉選び」が難しい場面が多いもの。
AIなら、感情に影響されず事実を整理して伝わる文章を作成できます。
「どう書けば角が立たないか」と悩む時間が減り、報告内容の精度が安定します。
2. 時間のロスを削減できる
1件の報告書に30分〜1時間かかることも珍しくありません。
AIが下書きを作ることで、入力から10分以内に骨子を作成できます。
修正・追記の時間も含めて、結果的に作業全体の半分以下に短縮できます。
3. 時系列や原因分析を整理してくれる
AIは入力された情報をもとに、「発生状況→原因→対応→再発防止策」を自動で構成します。
人がやると抜けやすい部分を補いながら、行政報告書の様式にも沿った構成に近づけられます。
4. チームで共有しやすくなる
AIの文章は標準的な表現で出力されるため、誰が読んでも理解しやすい報告書になります。
職員間の伝達ミスを減らし、共通認識を持ちやすくなる効果もあります。
AIを活かすコツ
AIを使うからといって、“丸投げ”ではうまくいきません。
次の3つを意識するだけで、完成度は大きく変わります。
- できるだけ具体的に入力する
「利用者が転倒した」ではなく、「トイレへ移動中にふらつきがあり、転倒した」など。 - 主観ではなく状況を伝える
「不注意だった」よりも、「段差に気づかず足が引っかかった」のように。 - AIの提案を確認し、自分の言葉を残す
AIはたたき台。最終確認は人の判断で。
「現場の実感を足す」ことで、信頼性の高い報告書になります。
介護現場でAIを使うメリットのまとめ
| 項目 | 効果 |
|---|---|
| 作成時間 | 約1/2〜1/3に短縮 |
| 精度・一貫性 | 客観的でミスが減る |
| 精神的負担 | 「責められる不安」から解放される |
| チーム共有 | 書式が統一され伝達しやすい |
| 学び | 事故を分析・再発防止策に活用できる |
AIを導入することは、「人を減らす」ことではありません。
人の判断と記録の間を支える仕組みとして使うことで、現場全体の質を高めることができます。
ということで、事故報告書作成用にカスタマイズされたChatGPTを用意しました!
「くよくよすんなよ、事故報告アシスタントちゃん」です(絶望的なネーミングセンス)。
事故報告専用AIチャットボット機能解説
簡単に機能を解説します。

チャットボットは、ユーザーが入力した内容に対して、適切な返答を返してくれるツールです。このチャットボットはChatGPT-4oでできており、AIが自然な会話で返答を出力します。ステップバイステップで、質問を重ねるようにしていますので、質問に応えるだけで、個人情報以外の部分に関しては事故報告書に必要な情報が揃うようになっています。
質問に応えたら事故報告書の文章がすべて出来上がっているというものです。
で、このAIはChatGPT-4oの学習データ以外にも独自データを学習させています。厚生労働省が作成した安全管理マニュアルや、介護労働安定センターの事故防止調査報告書などのデータを事前学習しています。つまり、過去の事故事例や事故の要因分析、再発防止策などについての情報を学習している、まさに事故報告専用AIとなっているのです。
そのため、ユーザーの回答した内容をもとに、類似した事例などを学習データから判別し、適切な改善策などを提案してくれるようになっているんです。
説明するよりも見てもらった方が早そうなので、こちらの動画をご覧ください。
チャットボットを動かしてみる
では、使ってみましょう。
チャットボットは、事故の種類を質問します。転倒や誤嚥など、事故の種類を選択します。
続いて事故発生の経緯について質問しますので、わかる範囲で時系列の情報を書きましょう。
発生時の対応、
医療機関への受診や診断結果、
利用者の状況、
家族への報告状況などを順に記入します。
これらの質問項目は、厚生労働省の作成した事故報告書のフォーマットに沿った内容となっています。
動画で見ている人、気づいたと思いますが、ちょっとした誤字であればAIも察してくれるので、気にせずガンガン書いていっちゃっていいです。
内容の入力が終わったら、チャットボットが自動的に事故の原因分析と再発防止策を考えてくれます。
書き出してくれた内容をそのままコピーして、報告書作成は完了です。

辛い思いを引きずらないように、サポーティブな声掛けをしてくれるチャットボットです。実はここに一番注力しました。事故報告にしっかり向き合ってくれた職員への暖かいねぎらいのメッセージを意図的に出力させるようにし、メンタル面のフォローを行うようにしています。
事故報告書って、書いて褒められることはあまりないでしょ(経験上)。でも、やっぱりメンタル的なフォローって絶対に必要な作業だと思うんですよね。それもAIにやってもらうようにお願いしています。AIは理想の部下にも理想の上司にもなりえるんですよね!
「AIが分析したなら、ま、そうなのかもな~」って話になれば、忖度なく、客観的な書類作成ができます。事故報告書の内容をめぐって感情の軋轢がなくなり、職場内の人間関係も良好になりますよね。
事故報告書として表が作成されたらとりあえず完成です。お疲れさまでした。
こんな追加質問するとさらに事故防止の意識が高まる
ちなみに、事故報告書を作るだけでなく、さらにこのチャットボットで次の施策に写ることもできます。
事故対応を評価してください
まず、「今回の対応を評価してください」とチャットボットに打ち込んでみましょう。今回の対応の良かった点や悪かった点なども教えてくれます。「100点満点で評価して」と質問すると、こんな返答をしてくれます。ちなみに、USBを紛失した個人情報漏洩の事例でデモンストレーションしています。
今回の対応を評価するにあたり、以下の観点を考慮します。
- 迅速な対応:
- 紛失に気づいた後、すぐに事務所内でスタッフに捜索を依頼した点は評価できます。
- 情報の把握:
- 紛失したUSBメモリーに含まれる個人情報の種類と人数を正確に把握している点も評価できます。
- 家族・関係者への報告:
- 利用者やその家族に対する連絡が行われていない点は改善の余地があります。
- 再発防止策の検討:
- 現段階では再発防止策の策定・実施が進んでいないため、今後の取り組みが必要です。
これらの観点から総合的に評価すると、今回の対応は60点と評価します。
ポイント
- 迅速な対応(20点中15点): 紛失に気づいた後の迅速な捜索は良かったですが、さらに全体的な捜索手順の見直しが必要です。
- 情報の把握(20点中20点): 紛失した情報の種類と人数を正確に把握している点は非常に良いです。
- 家族・関係者への報告(20点中5点): 利用者やその家族への報告が欠けている点は改善が必要です。
- 再発防止策の検討と実施(40点中20点): 再発防止策の検討をこれから行う必要があります。
このつらい経験を通じて改善すべき点を見つけ、次回の対応に生かしていくことが重要です。あなたの努力は、今後の安全な介護につながりますので、引き続き頑張りましょう!
おお。すごい。指摘することは指摘していますが、丁寧に言葉を選んでいるので痛くない。ちょっと甘々判定な気がしますが、課題はしっかり見えますね。
再発防止のための研修プログラムを作って
再発防止のための研修プログラムを作って、とお願いするとAIが研修プログラムを考えてくれます。めちゃくちゃ長い時間のプログラムを考えてくることもあるので、そこは事業所・施設で研修ができる時間を考慮して、30分以内で、とか60分以内でとか、条件を書けばいいです。こんな感じにまとめてくれます。
30分から40分程度で実施できる研修プログラムを以下のようにコンパクトにまとめました。
情報漏洩防止短時間研修プログラム
1. 目的
- 職員に対する情報管理の意識向上
- 情報漏洩のリスクを低減するための基本的な対策の共有
2. 対象
- 全職員(特に情報を扱う機会が多い職員)
3. 研修内容
以下のセッションで構成される30分から40分の研修プログラムを提案します。
セッション1: 情報漏洩の基礎知識と影響(10分)
- 目的: 情報漏洩の基本的な概念とリスクについて理解する
- 内容:
- 情報漏洩とは何か
- 情報漏洩の主な原因と影響
- 近年の情報漏洩事例の簡単な紹介
セッション2: 具体的な対策と手順(15分)
- 目的: 情報漏洩を防ぐための基本的な手順と対策を学ぶ
- 内容:
- 情報の持ち出しと返却に関する基本手順
- USBメモリーの管理方法
- 物理的な管理強化のポイント(例: ログの記入、専用ケースの使用)
- デジタルセキュリティ対策(例: パスワード管理、暗号化)
セッション3: 質疑応答とまとめ(5分〜15分)
- 目的: 研修内容の確認と疑問点の解消
- 内容:
- 研修内容の簡単なまとめ
- 質疑応答の時間を設け、疑問点を解消する
- 重要なポイントの再確認
4. 研修資料
- 簡潔なパワーポイントスライド
- 情報漏洩防止のチェックリスト
おお。素晴らしい。ちなみに、パワーポイントスライドのアウトラインを作ってもらうこともできますし、情報漏洩防止のチェックリストを作ってとお願いすれば、チェック蘭付きのチェックリストも作ってくれます。
まとめ
辛いことはAIを使うことで、より冷静に、客観的に評価することができ、介護職員のモチベーション維持にも役立ちます。
ChatGPTの事故報告アシスタント、ぜひ使ってみてくださいね。
もちろん無料で使えます。
※ChatGPTを使うのでChatGPTの無料アカウントへの登録は必要です。まだChatGPT使ったことがない!って人は作っておいてください。無料アカウントでも絶対あれば便利なので。
ウェルコネクトでは介護現場でのAI活用・業務効率化に関する質問も随時承っていますので、ぜひお気軽に。Youtubeチャンネルでも情報発信していますので、業務改善にAI使いたい方はとりあえずチャンネル登録を!

編集:
介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)
ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。



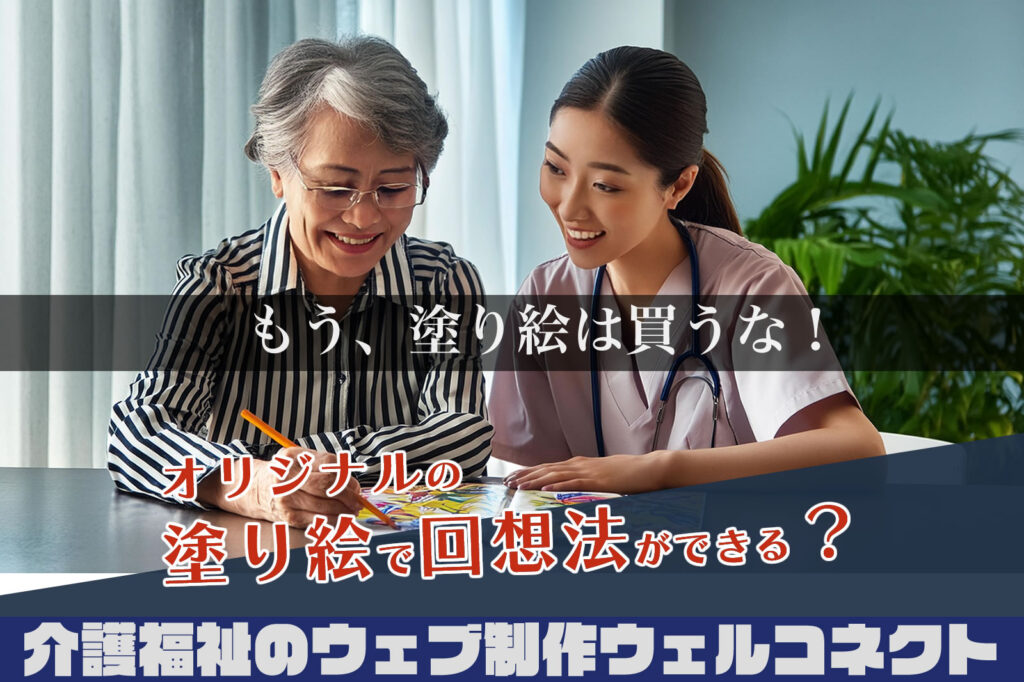

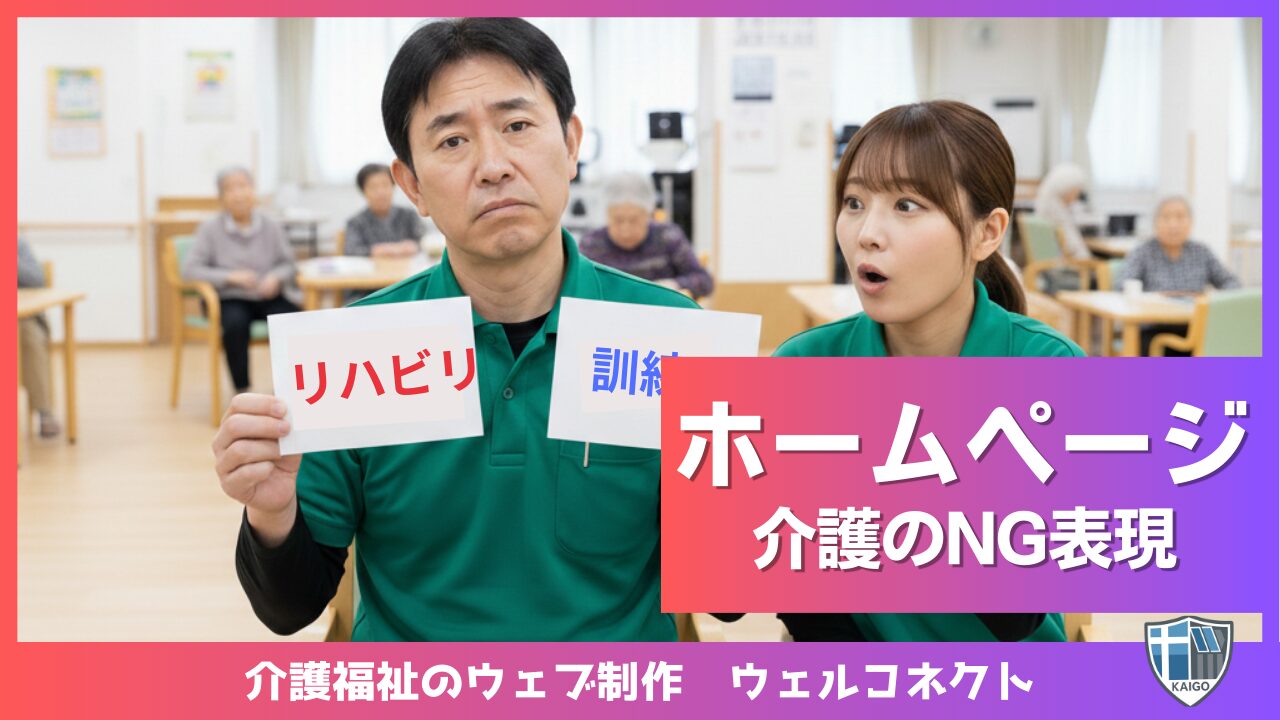


“事故報告書はAIに!介護現場の事故報告専用無料作成ChatGPT解説!” への1件のフィードバック