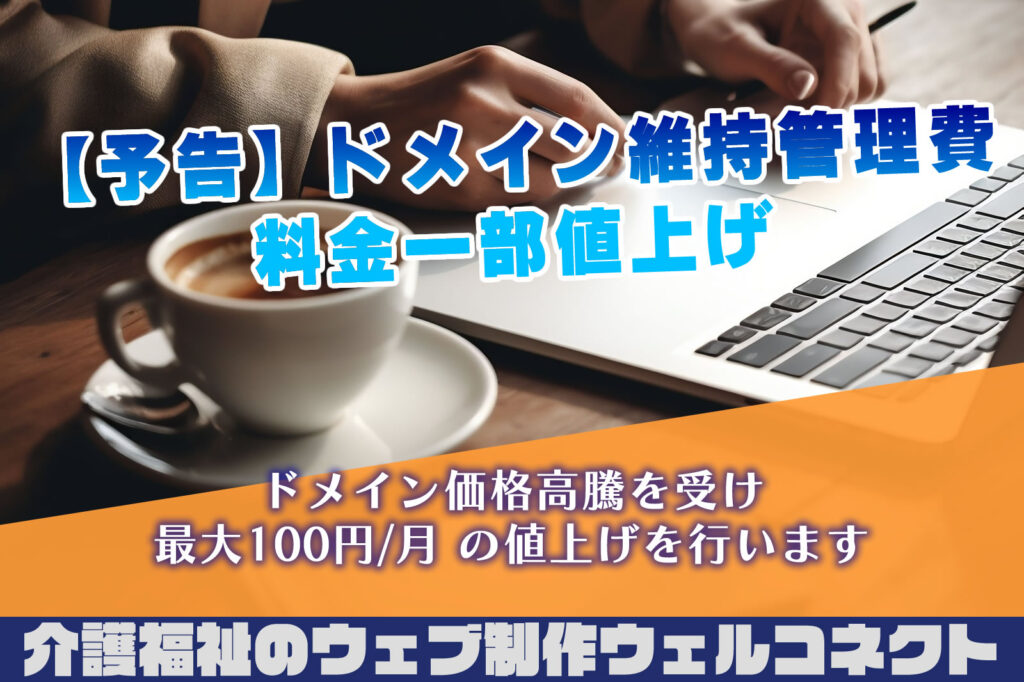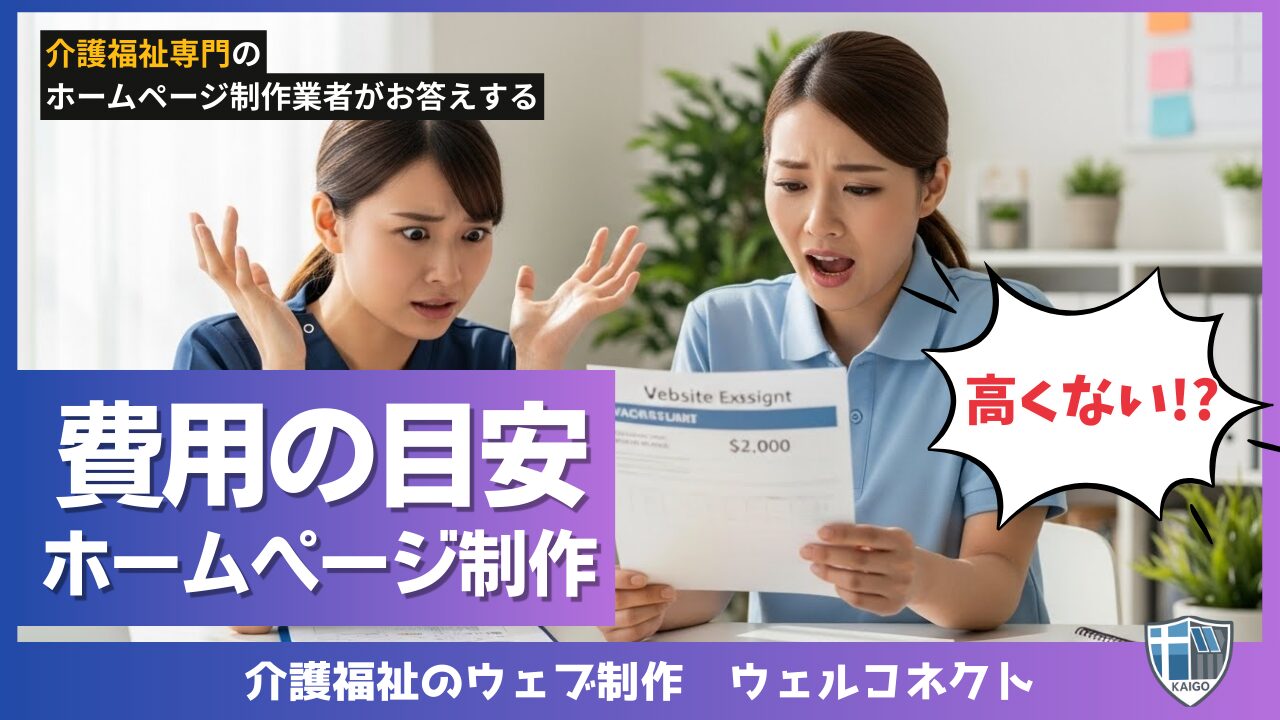この記事のコンテンツ
ドメインがユーザーにもたらすインパクトとは?

「ドメイン」という言葉を聞いたことがありますか?
ドメインとは、一般的には「領域」や「領土」などを意味する言葉なのですが、
インターネット上でサイトやメールの“住所”を表す文字列として使われることが一般的です。
正式には「ドメイン名(domain name)」と呼ばれ、
ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers:
インターネットの識別子を管理する国際機関)によって定義されています。
ICANNの説明によれば、ドメイン名とは「インターネット上でのリソースを識別し、
人が理解しやすい形でアクセスできるようにする名前」です。
数字で構成されたIPアドレスを、人が読める文字列に置き換える役割を持ちます。
たとえば、ブラウザのアドレスバーに表示されるhttps://www.welconnect.netで言えば、「welconnect.net」がドメイン名です。
本来であれば、IPアドレスという数字の羅列で表記されるインターネット上の住所を、ドメインという文字列にすることで、その場所にたどり着きやすくなる。というのがその起源です。
いまや、世界中には数億・十数億というドメイン名があると言われています(2019年の情報では3億5980万件のドメインがあるという情報がありました)。
※インターネット白書2020「ドメイン名の動向」
たかが住所、されど住所。ドメインの持つ意味
検索エンジンで何かを調べると、
サイトタイトルや説明文とともに、ドメイン名も表示されます。
ドメイン名から、その発信元がどんな事業を行っているのか、どんな地域で行っているのかなどを連想することができます。
たとえば、介護事業所が「care」や「support」といったドメインを使っていれば、
閲覧者は一瞬で「介護・支援に関するサイトなんだ」と認識できます。
反対に、意味のない文字列が並んでいると、どんな事業なのかが伝わりにくく、
信頼やクリック率にも影響します。
「.jp」であれば日本国内で事業が行われているのだなと印象付けることもできます。
ドメイン名は「ただの住所」ではなく、
その事業の印象やブランドを形づくる要素のひとつと言えるでしょう。
独自ドメインの構造とルール
独自ドメインでは、ドット(.)の前にくる部分を自分で自由に決めることができます。
たとえば「welconnect.net」であれば、「welconnect」が自分で決めた部分です。
ただし、ドメインは早い者勝ち。
一度ほかの誰かに登録された名前は、同じ形では取得できません。

一方、ドットのあとの部分は「トップレベルドメイン(TLD)」と呼ばれます。
よく知られているのが .com(商用)、.net(ネットワーク)、.jp(日本) など。
TLDには大きく分けて以下の種類があります。
| 種類 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 分野別トップレベルドメイン(gTLD) | .com、.net、.care、.support など | 世界中の誰でも登録できる汎用ドメイン |
| 国別トップレベルドメイン(ccTLD) | .jp(日本)、.uk(イギリス)など | 国や地域を表す。取得要件がある場合も |
| 属性型JPドメイン | .co.jp、.or.jp など | 日本国内で登記を行う企業・法人のみ登録可 |
このうち、.co.jp などの属性型JPドメインは法人登記が条件となるため、
小規模事業所や個人事業主の場合は、.jp や .com を選ぶのが一般的です。
こうしたトップレベルドメイン(TLD)のうち、
.com や .net といった「分野別ドメイン(gTLD)」には近年大きな変化が起きています。
選択肢の広がるトップレベルドメイン(gTLD)
ここ数年、ドメインの中でも特に gTLD(generic Top Level Domain:分野別トップレベルドメイン) に大きな変化がありました。
かつてgTLDといえば、.com や .net、.org など限られた種類しか存在していませんでした。
ICANN(インターネットのドメイン名を管理する国際機関)の資料によると、
2011年までは世界で22種類のgTLDしか認められていなかったとされています。
しかし2012年以降、ICANNが「新gTLDプログラム(New gTLD Program)」を開始し、
業種・地域・ブランドなどを表す新たなドメインが一気に増加しました。
その結果、現在では1,000種類を超えるトップレベルドメインが登録・運用されています。
(※出典:ICANN “New gTLD Program” https://newgtlds.icann.org)
トップレベルドメイン自体が意味を持つ時代へ
新しいトップレベルドメインには、それ自体に明確な意味があります。
ドメイン名を見ただけで、サイトの地域・業種・目的をイメージさせることができるのです。
たとえば、
- .tokyo / .yokohama といった地域名ドメインなら、活動エリアをストレートに伝えられる
- .care / .support / .clinic といった業種別ドメインなら、サービスの内容を印象づけられる
- .shop / .blog / .media などであれば、目的や形態をすぐに理解してもらえる
つまり、新しいgTLDの登場によって、
「トップレベルドメイン自体に意味を持たせる」ことが可能になったのです。
これまでのように「.com=何でも屋」ではなく、
ドメインを選ぶこと自体が、ブランディング戦略の一部になりました。
介護事業所におすすめのトップレベルドメインとは?
では、介護事業所にとってどんなドメインが適しているのでしょうか。
ここでは、ウェブ制作の現場とドメイン登録動向(ICANN・JPRS等のデータ)を踏まえて、介護業界にマッチするトップレベルドメインを紹介します。
介護サービス事業所全般におすすめ
| ドメイン | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| .care | ケア | 「介護」や「ケア」を直感的に伝えられる。海外でも福祉・医療分野で人気。 |
| .support | サポート | 利用者支援・相談対応など、“寄り添う姿勢”を表現。 |
| .help | ヘルプ | ボランティア・相談窓口など、人を助ける印象を与える。 |
たとえば事業所名が「ひまわりサポート」なら、
himawari.support というドメインも登録可能です。
事業所名とドメイン名が自然に結びつくと、ブランドの統一感と信頼性がぐっと高まります。
採用・求人関連サイト向け
| ドメイン | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| .careers | キャリア | 求人・転職サイトに最適。人材育成やキャリア支援の印象を持たせられる。 |
| .jobs | ジョブ | 短く覚えやすい。Indeedなど大手も活用しており、認知度が高い。 |
例:kaigo.jobs
シンプルかつ業種特化型で、介護業界の求人サイトとして非常にわかりやすいです。
福祉系専門学校・研修機関におすすめ
| ドメイン | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| .academy | アカデミー | 学校・教育・研修に最適。資格取得講座や職員研修にも。 |
| .education | エデュケーション | 教育機関全般に使える。公式感が強く、信頼性を高めやすい。 |
「介護職員初任者研修」「実務者研修」などを扱う学校なら、
kaigo.academy のようなドメインが直感的でおすすめです。
福祉用具販売・レンタル事業者におすすめ
| ドメイン | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| .shop | ショップ | オンラインストア向け。物販型サイトに最適。 |
| .store | ストア | 実店舗のブランドサイトにも使いやすい。 |
| .rentals | レンタルズ | 介護ベッド・車いすの貸与業者などに。レンタル専門の印象を明確に。 |
たとえば、会社のメインサイトとは別に
kaigo.shop としてEC展開するなど、用途を分けて使うのも効果的です。
医療・介護連携事業所向け
| ドメイン | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| .clinic | クリニック | 医療法人・訪問看護ステーション・併設クリニックに。 |
| .dental | デンタル | 歯科医院・訪問歯科事業に。 |
| .center | センター | 「相談センター」「地域包括支援センター」などの名称に合う。 |
例:fujisawa-clinic.jp や kaigo.center
地域密着型の印象を強める効果があります。
コンサルティング・経営支援事業向け
| ドメイン | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| .consulting | コンサルティング | 介護経営・加算算定・運営支援などの専門サイトに。 |
| .management | マネジメント | ケアマネ支援、経営管理、マネジメント研修などに最適。 |
「care.management」は残念ながら既に取得済みですが、
地域名を加えた kanagawa.management のような形ならまだ取得可能な場合があります。
デイサービス・リハビリ系事業所におすすめ
| ドメイン | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| .fit / .fitness | フィット・フィットネス | 「運動を通じた介護予防」などを訴求するデイに。 |
| .salon | サロン | “集う場所”を連想させる。地域コミュニティ色を出したい場合に。 |
| .services | サービス | 「day.services」「care.services」など応用範囲が広い。 |
例:ebina-day.services(海老名デイサービス)
地域とサービスを両立した命名が可能です。
グループホーム・入居系施設におすすめ
| ドメイン | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| .house | ハウス | 有料老人ホーム・グループホームに自然。 |
| .rest | レスト | ショートステイやリハビリ休息型施設に柔らかい印象を与える。 |
新たに注目される介護系ドメイン(2025年版)
| ドメイン | 読み方 | 用途例 |
|---|---|---|
| .life | ライフ | 在宅介護・終活支援・生活支援サービス全般に。 |
| .community | コミュニティ | 地域包括・自治体連携・多職種ネットワークに。 |
| .homes | ホームズ | 入居施設や住宅改修事業者にもマッチ。 |
これらは新gTLDの中でも、福祉・地域・生活に直結するワードとして
今後の介護業界ブランディングにおいて注目されています。
変わったドメインを使うことのメリット・デメリット
ドメインの選択肢が広がった今、
「.comや.co.jpではなく、ちょっと個性的なドメインを使ってみたい」
という事業所も増えています。
ただし、“印象に残る”ことと“信頼される”ことは必ずしも同じではありません。
ここでは、新しいgTLDを活用するうえでの長所と短所を整理します。
メリット:差別化とストーリーづくり
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ① ブランディング効果が高い | サービスの方向性や理念を、ドメイン名そのものに込められる。例:mirai.care → 「未来をケアする」など印象的に伝えられる。 |
| ② SEO・SNSでの印象が良い | 検索結果やシェア時のURLが短く、意味を持つため覚えられやすい。クリック率(CTR)が上がるケースも。 |
| ③ サブブランド展開に向く | 法人サイトと切り分けて、採用サイトや研修サイトなどを個別運営しやすい。例:company.co.jp + recruit.careers など。 |
| ④ ドメイン名が取得しやすい | .com や .jp ではすでに埋まっている文字列も、新gTLDなら空きが多い。 |
デメリット:信頼性と運用コスト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 認知度がまだ低い | 一般利用者には「聞き慣れないドメイン=怪しい」と思われる可能性がある。特に高齢層の利用が多い介護業界では慎重な判断が必要。 |
| ② 一部メールシステムで弾かれるリスク | .shop や .xyz など一部の新gTLDは、迷惑メール判定を受けることがある。運用前にメール送受信のテストを行うのが望ましい。 |
| ③ 更新費用がやや高い | 新gTLDは登録機関によって年額が高めに設定される場合が多く、年間2,000〜6,000円台が一般的(.jpや.comより高い)。 |
| ④ サービス終了リスク | 一部gTLDは採算が取れず廃止されることも。ICANNにより管理移管されるが、念のため契約レジストラの信頼性を確認しておく必要がある。 |
介護業界における現実的な戦略
- 法人サイトは信頼重視で「.jp」や「.co.jp」
- 採用・広報・地域活動サイトは印象重視で「.care」「.support」「.life」
- サブドメインや別ドメインを活用して両立する
たとえば、
- 公式サイト →
kaigo.jp - 採用専用サイト →
kaigo.jobs - 地域活動ページ →
kaigo.life
このように役割を分けることで、
安定性と柔軟性を兼ね備えたドメイン戦略が可能になります。
一般的には、サブドメインといってドメインの前に文字列をつけてホームページを分ける方法がよくつかわれます。
例えば、採用サイトであれば、recuirt.kaigo.jp のようなドメイン名を使うことが多いです。
ただ、一発でサイト名を見たときの印象は、より少ない文字列でインパクトを持って伝えられるので、だいぶ違いますよね。
ドメインも「第一印象の設計」
ドメインは、サイトを開く前にユーザーが“見る最初の言葉”です。
そこに事業の理念や方向性を込めることで、
検索結果の一行だけでも「何を大事にしているか」が伝わります。
変わったドメインを使うこと自体が目的ではなく、
「誰に、どんな印象で、どう見せたいか」を考えることが本質です。
ドメインは、戦略の一部として選ぶ時代に
ここまで見てきたように、ドメインの世界はここ数年で大きく広がりました。
かつては「.com」か「.jp」しか選択肢がなかった時代から、
今では業種・地域・理念を反映できる多様なトップレベルドメイン(gTLD)が登場しています。
つまり、ドメインはただの住所ではなく、“事業の意図を伝える表現ツール”へと進化したのです。
ホームページづくりにおける新しい選択肢
- 新しく立ち上げる事業所のホームページに
- 採用サイトやキャンペーンなどのサブサイトに
- 既存サイトのブランド再設計に
「名前」そのものを戦略的にデザインする感覚で、
ドメインを選ぶ時代に入っています。
コストと計画の重要性
一方で、新しいgTLDは従来よりも維持費が高めに設定されています。.com や .jp が年間2,000円前後なのに対し、.care や .support などの新gTLDは3,000〜6,000円前後が一般的です。
世界的にもドメイン費用は上昇傾向にあり、
レジストラ(登録業者)によって更新料が異なるため、
長期的な運用コストを見据えた計画的な取得が大切です。
この記事を最初に書いた2018年から2025年までの間に実は倍近く上がってます。
私共も大変心苦しいところでしたが、ドメインの料金の値上げをさせていただきました。
最後に、ひとつだけ
ドメイン名は早い者勝ちです。
一度ほかの誰かが登録してしまえば、
同じ文字列ではもう取得できません。
「この名前にしたい」と思った瞬間が、
実は一番のチャンスです。
ブランディングも信頼構築も、
一つのドメイン名から始まります。
ドメインに関するよくある質問
ドメイン管理機関や登録業者への支払いのため
ドメインは勝手にだれでも発行していいものではありません。同じドメインがこの世に2つ存在しないように管理がされているのです。
ドメインにはドメインを管理する管理機関があります。それがレジストリという管理機関です。
ドメインの金額は管理機関や登録業者に支払わなければいけません。この金額がそれぞれ異なるため、ドメイン費用に違いがあります。
基本的にはないとされています。
ドメインは○○.com、○○.net、○○.jpなど、いわゆるホームページ上の住所です。
ホームページだけでなく、このドメインを使ってメールアカウントの作成も可能です。
ホームページ上の住所でもあり、看板でもあると思ってください。
.comや.jp、.jp、.co.jpなど、ホームページのドメインには様々な種類があります。
ドメインに何を選んだら検索エンジンの表示で優位になるかという質問をいただきますが、基本的には新規に取得する場合のドメインの種類で検索の優位性に大きな違いはありません。すくなくとも、Googleはそう公表しています。
.co.jpや.or.jpなどは、確実に国内にある企業であることを証明しなければいけないなど、国を示すドメインもあります。日本国内の企業であることをアピールしたい場合はjpドメインを取得することもひとつの方法です。
新規で取得する場合は、そのドメインがどんな企業が、どんな専門性を持っている事業者なのかをアピールし、Googleやユーザーからの信頼を高めていくことが大切です。ドメインは育てていくものです。○○.comのドメインは、看護に関する情報に詳しいから、このドメインで公開されている情報は信頼性が高い!とGoogleに認知してもらえれば、ドメインの価値が高まり、検索順位も高くしてもらうことができます。
ちなみに、いつもお世話になっているドメイン管理会社がこちらのバリュードメインさんです。ドメインとサーバーを同時契約すれば一部のドメインは無料となります。
通常、サーバーは別会社のサービスを利用しているのですが、ランニングコスト、ドメイン費用を少しでも安くしたい、というご希望があれば提案させていただくことも可能ですので、ぜひお声掛けください。

編集:
介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト編集部(主任介護支援専門員)
ケアマネジャーや地域包括支援センターなど相談業務に携わった経験や多職種連携スキルをもとに、介護福祉専門のウェブ制作ウェルコネクトを設立。情報発信と介護事業者に特化したウェブ制作サービスとAIを活用した業務改善提案を行う。